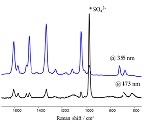「光の非弾性散乱」、すなわちラマン効果は、1928年にC.V.ラマンによって初めて観測され、彼は1930年にノーベル賞を受賞しました。しかし、ラマン分光法が材料科学や生命科学の応用からポイントオブケア分析に至るまで、ほぼ普遍的に適用可能な分析技術としてその可能性を実現し始めたのは、ここ20年ほどのことです。これは主に、小型レーザー光源、高感度カメラ、高解像度小型分光計の普及によるものです。 この技術の物理的基盤は、姉妹技術である赤外分光法と比較して、非常に柔軟性と利点に富んでいますが、同時に重要な課題も存在します。励起は、(i) 単色性(ラマンバンドが光源と同じ形状であること)、(ii) コリメート性、(iii) 高強度(非弾性散乱の確率が低いため、光子106個中1個未満)であることが求められます。したがって、レーザーの登場こそが、文字通りラマン分光法をこの分野にもたらしたのです。